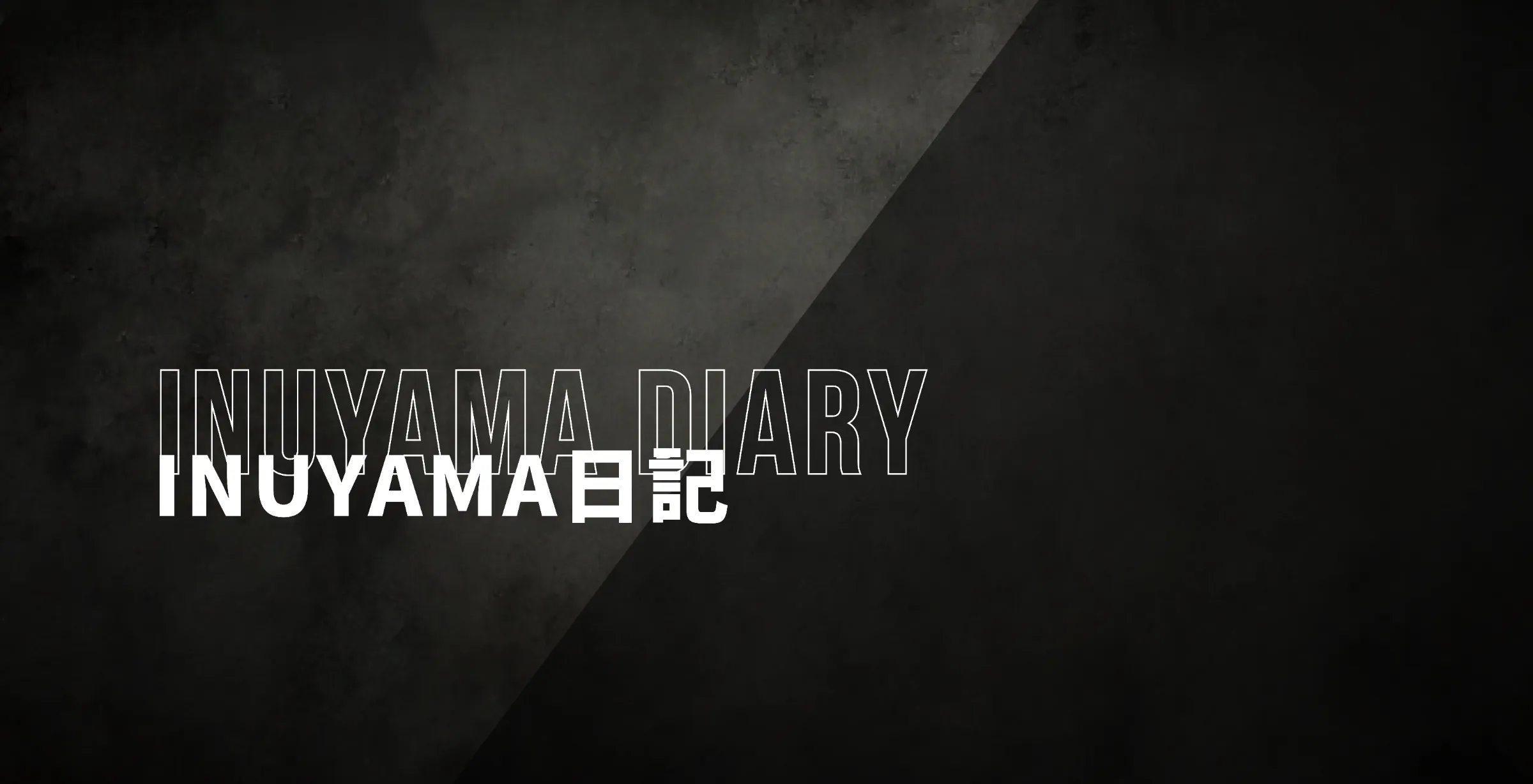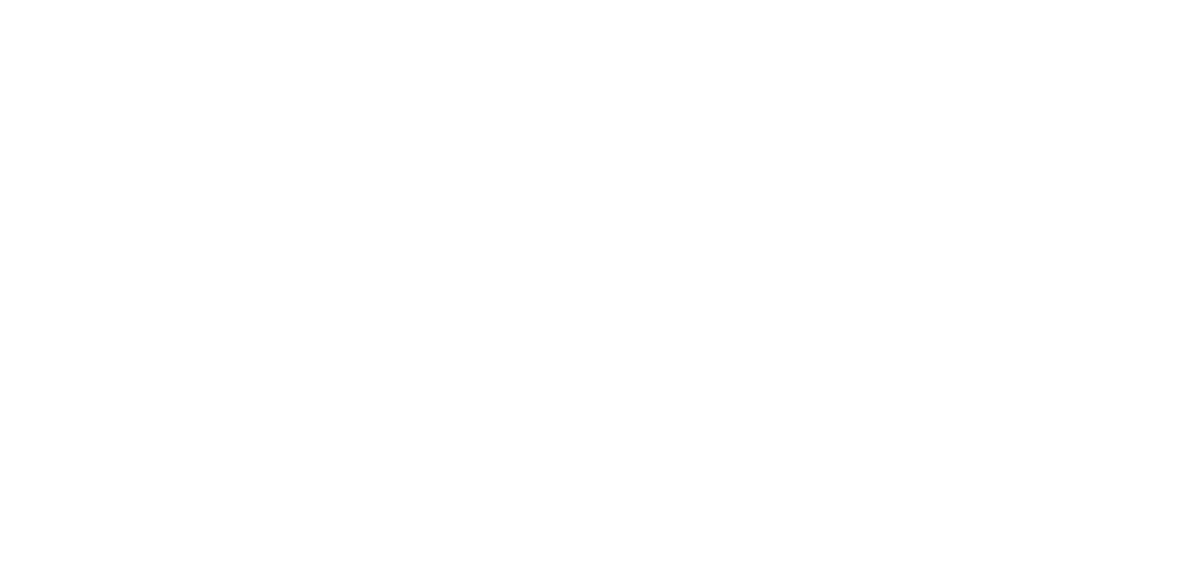#137 ABC理論
2025/03/12 12:50

2025年3月11日はジュニアの全体練習でした。先週は一週間GR TOURでアメリカへ行っていたため自分が練習をみること自体は約1週間半ぶりとなりましたが、不在の期間も三品コーチやリーダー陣が中心となってやってくれていました。
第一タームに設定している1月〜3月では、声や取り組み方などの「基準」を高くすることを口酸っぱく言い続けてきましたが、1月と比較すると一人一人の当事者意識も高まってきていて練習に良い緊張感が生まれているように感じます。
声はただ出すだけではなく体育館に響き渡るくらい、もしくは声が枯れるほどに出す。もちろん声の内容(質)にもこだわりたいですが、まずは雰囲気づくりも含めて大きさ(量)を優先しています。
また、取り組み方の部分においては100パーセントではなく101パーセントを目指し、物差しの基準をアップデートしていくことで限界を越えていくことを求めています。前にも話をしたようにA君の100%とB君の100%は違うので、いつでも全力だけでは足りず、プラスワンを毎日の練習から求めていきたいです。
ここ最近のゲームではディフェンスの一線の間合いの感覚が向上してきていて縦に破られるケースはほとんどなくなりました。シェルディフェンスはまだポジショニングしかやっていないですがこれからパターンを増やしていき、失点はある程度抑えられる状態に持っていけると思っています。
一方で24秒守り切った後のリバウンドは課題が残りました。2、3つで連続でオフェンスリバウンドを握られてせっかく良いディフェンスができた時間帯を無駄にしてしまうシーンがまだあります。ディフェンス→リバウンド、リバウンド→ブレイクと局面ごとの繋がりを持たせるためのトレーニングを今週来週と続けていき、桜台カップでは課題を克服した状態で試合をしたいです。
オフェンスでは、DFに間合いを近くされた時のプレッシャーリリースと考え方を伝えました。激しく距離の近いDFに対して、プレッシャーに感じてミスを恐れるのか、カウンターのチャンス、又はファウルを貰えるチャンスだと捉えてプレーするのかは全く結果が異なります。ABC理論という考え方も合わせて伝えましたがどんな捉え方をするかで未来は変わります。次同じようなDFをされた時はラッキーだと捉えて遊ぶようにプレーできると良いですね。
▼ABC理論
https://www.awarefy.com/coglabo/post/abc_model
ウォーミングアップとして取り入れているグループワークでは、シューティングドリルに「得点のカウント」の要素を加えてみました。
①シュートキャンセル→カウンター
②ヘルプ判断(ストップショットorレイアップ)
③キャッチ&ショット(3P)
④ライブ判断
※外したらリバウンドして決めるまで
今日試してやった結果、Aグループは時間内に100得点、Cグループは120得点。高得点を狙うために、一人一人のシュートの確率も当然ありますが、外した時に素早くリバウンドしてゴール下を決めることや、ドライブのスピード感など、要素がたくさんあります。得点をカウントさせることによってよりゲームライクになることやグループ間競争も生まれてメリットが大きいのでしばらくの間、継続していきます。
同じメニューのなかでも常に考え続けてよくなる仕組みへと改善していく。リーダー陣がこれをできるようになったらもっともっとグループワークも効果が高まっていきそうです。
#すべては自分の捉え方次第