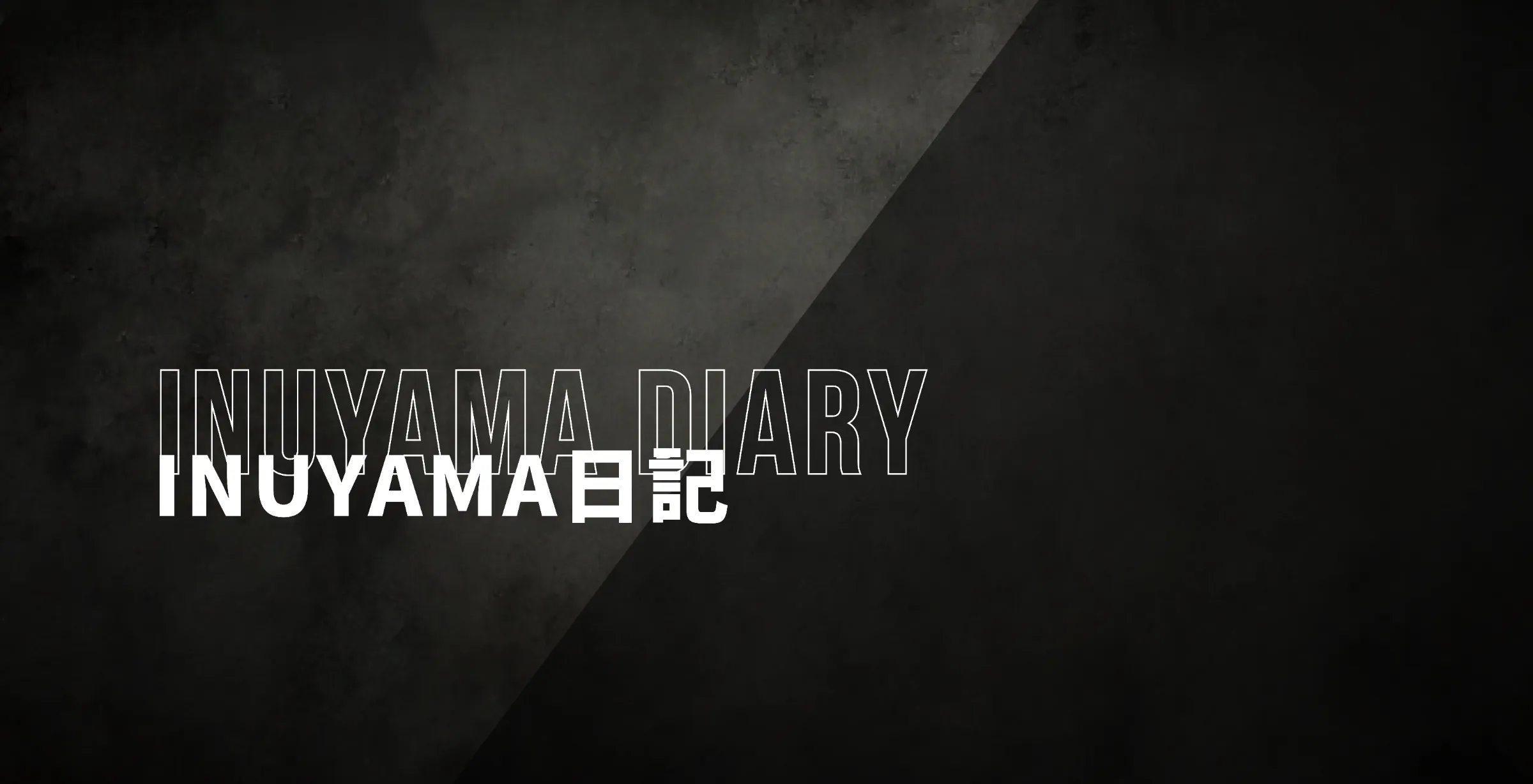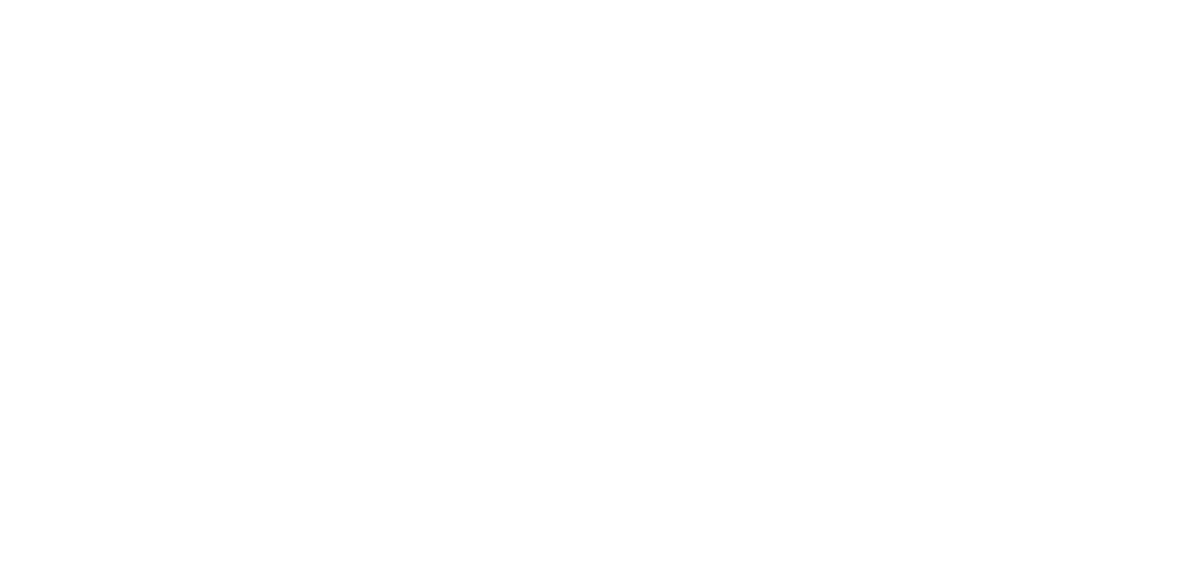#91 U12東海DC
2025/01/25 19:24

2024年9月7日、8日はU12東海DCの講習会が静岡で開催され参加させて頂きました。
東海4県(愛知・岐阜・三重・静岡)男女のDCスタッフが集合して、1日目はJBAからの伝達講習会(インプット)2日目はヘッドコーチの皆さんがモデル生(浜松地区の選手達)に対して1日目の講義内容を踏まえた実践指導(アウトプット)をおこなうカリキュラムでした。
今年は「パス」がテーマになっていて、チェストパスやバウンズパスなど基礎的なものだけではなく、オーバーヘッドパス、ラテラルパス、様々な種類のパス投げられるファンダメンタルを身に付けつることと、そのうえで相手を感じて使い分けをできるような選手(観れる)の育成を目指すことの重要性が語られていました。
▼思えばちょうど5年前..
2019年12月8日、9日に愛知県開催だった同じ講習会に当時はDCのスタッフではなかったので勉強として参加をさせて頂きました。
この時の懇親会は強烈に印象に残っていて.. 各県で実績を出されているチームのコーチの方達の圧倒的な熱量、学びへの貪欲さ、勝ちたい気持ち、まだまだコーチとして歩み始めた頃だった自分からしたらその当時の甘さを間接的に突きつけられたような時間でした。
思い返してみればそのときの衝撃から「量」の重要性に気が付き、皆さんと同じことをやっていたら一生追い越せないと確信したので、ジュニア立ち上げ、オンライン練習、SNS活用などなど、自分にできる色々な挑戦をしてきて今に至ります。
携帯のメモを見返していたら当時のものがあったので記念に残しておきたいと思います📝
—
▼2019/12/07-12/08 東海U12DC
http://www.japanbasketball.jp/training/documents/
【1日目】
●佐藤 晃一さん(JBA)
https://ameblo.jp/ks-gettingbetter/
https://basketballking.jp/news/world/nba/20170223/7616.html
●水分補給は喉が乾いてから?
・こまめに飲むという考えはNG
・スポーツドリンクを売りたい人が広めた(マーケティング)
●スタティックストレッチをやるとパフォーマンスが落ちる?
・すぐにやれば落ちるがストレッチによって得られる効果を考える
●インターバル走から早く回復するためには?
・膝に手をついて回復するのが実は一番良い
●ここに来れた方法で次の目的地にはいけない
・今までの当たり前は当たり前じゃない(時代の変化を捉える)
●問題解決における最大の障壁は人間の心
・自分をいかにアップデートし続けることができるか
●マインドセット
・固まったマインドセットの人 ⇒ 失敗=ネガティブなイメージ
・成長マインドセットの人 ⇒ 失敗=学びの機会と捉える
https://achievement-hrs.co.jp/ritori/?p=1578
●褒め方(簡単なテスト or 難しいテスト)
・「知性」を褒めたグループ(頭がいい 等)
⇒ 7割以上が簡単なテストを選ぶ
⇒ 壁にあたるとすぐに諦めるようになる
⇒ できることだけやるようになる
・「努力」を褒めたグループ(ナイスチャレンジ 等)
⇒ 9割以上が難しいテストを選ぶ
⇒ 壁があっても粘り強くチャレンジする
⇒ できないことをやるようになる
●ヨーロッパの選手に比べると日本選手は問題解決能力が低い
・ヨーロッパの指導者:課題を与える(子供に解決させる)
・日本の指導者:すぐに答えを与える
⇒ 選手が主体的に課題を解決する指導をしなければいけない
●日大アメフト部
・できるできない問わず時間毎に練習を変えていく
・できるようになるまでやる練習が多い
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20191206-00841730-number-spo
●膝は前に出してもOK
・確かに負担はかからないがかかと重心では動けない
・スクワットは足首〜膝〜股関節と均等に力を入れる
●関節
・動きやすい方が良い部分と動きにくい方が良い部分がある(階層状態になっている)
●犬がしっぽを動かすかしっぽが犬を動かすか(体幹)
・犬がしっぷを動かす(胴体の軸がブレていない)
・しっぽが犬を動かす(しっぽを振ろうとして胴体が動いている)
・腰椎を固定して周りの関節を動かす
●バスケットボールは早くはじめて遅く特化(早期特化)
・6〜8歳ではじめた方が良い(ボールを扱うため)
・でも特化するのは15歳から(他の競技をやらせる)
・多種目アスリートは単種目アスリートに比べて選手生命が長い
【2日目】
●鈴木 良和さん(JBA)
https://ameblo.jp/basketballtutor/
●ボディーアップ(コンタクト)
・骨盤、両肩の四角形の中心でオフェンスを捉える
・コンタクトは筋肉の量ではなくスキル(いつ、どこで当たるか)
・世界ではスタンダードなので当たられてもガードは全く慌てない
●5アウトオフェンスを推奨(スペーシングを学べる)
・ドライブ&キックアウト
・パス&カット(コーナー)
・ドライブに対するスペーシング(渦の理論)
・ボールから遠ざかる
●1対1の打開力強化
・スクリーンなどに対するDFは整理されている
・期待値を高めるためにクローズアウト、ギャップ、ミスマッチの状況をつくる
●課題解決能力強化
・コーチの指示ではなく選手がコート上で判断できるように
・育成年代から自分で考える癖をつけなければいけない
・教えすぎないように気をつける
●カンテラTV
・スペインバスケットが見れる(YouTube)
●シューティングプロジェクト
・3分で最低35/50を目指す(7割)
・ただシューティングしていれば入るようになる訳ではない
・まずはスポットシューティングの精度を高める
・上下左右のステップからプルアップジャンパーを打てるように
・クイック3P
・1カウントで打って入るようにする(2カウントで今は打てても世界では打てない)
・ボールとリングの間は約10センチもある(外すことの方が難しい)
・高い軌道はアーチの再現性を出しにくいが面積は広がる(技術で苦しみ結果で楽をする)
・低い軌道はアーチの再現性を出しやすいが面積が狭まる(技術で楽をして結果で苦しむ)
https://apps.apple.com/jp/app/homecourt-the-basketball-app/id1258520424
【懇親会にて】
(JBA佐藤さん)
●パワーポジションの適切な足幅はあるか?
・骨盤など全ての人が違うため必ずこの幅というものはない(No)
・基準として肩幅より広めが良いということだけは伝える
・適切な足幅は選手が自分で見つけなければいけない(同じではない)
・横からの圧力に強いスタンスだが背筋が少しでも曲がっていると弱くなる
・適切な足幅かつ上半身の姿勢が大事
●OFリバウンドの局面でボックスアウトされてもDFの背中を押してバランスを崩せるか?
・後ろからの圧力に弱いスタンスなのでOFはそれを狙わないといけない(Yes)
●DFリバウンドの局面でヒット(半身で当たる)1stなのは押し込まれにくくするためか?
・初めから背中で当たると押しに弱いため高い相手に後ろから取られやすい(Yes)
●代表選手で体の使い方が上手い選手は誰か?
・理想が高すぎるのでこれだと思える選手がいない
・富樫選手は反り腰(体の使い方は良くない)
●スライドで進行方向と逆の足で蹴り出した後は引きずるか or 引きずらない方がいいか
・どちらでも良いが引きずるとブレーキになるので引きずらない方が良いとは思う
・明確な根拠がある訳ではない
●できないプレーがある=スキル不足ではなく体の使い方ということもあるか?
・体の使い方が改善されてできるようになったプレーが増えることは多々ある
・代表レベルの選手でも体の使い方をわかっていない選手が多い
(JBA鈴木さん)
●課題解決能力強化のために特に育成年代のコーチは教えすぎないことを優先するとあったが判断基準を教えることは教えすぎにあたるか?
・何も教えないのは放任になるので判断基準を教えることはOK
・子供が選んだ判断に対してこうだろうと決め付けてはいけない
・一度決め付けるとそれをやろうとして結果子供は考えなくなる
●バスケットにおいて育成年代からの教えすぎの文化が選手の課題解決能力が低いことを生んでいる要因だと仮定した時、同じ文化の中でも結果が出ている他の競技はどんな理由が考えられるか?
・大抵はクローズドスキルが求められる競技が多い(陸上やゴルフなど)
・例えばアルゼンチンはヘルプDFを教えるのも中学3年生くらいから
・抜かれると誰も助けてくれないから抜かれないように工夫するようになる
・ピック&ロールなど簡単に点が取れるプレーを教えるのはナンセンス
・簡単に点を取れれば次第に工夫しなくなる
・ブロックNG、スティールNGの練習ではオフェンスは育たない
・日本ではブロックに飛んでこないような状況で世界は手が届いてくる
・チャンスがあればいつでもボールを奪いにいくディフェンスがオフェンスを育てる
・オフェンスリバウンドにいく選手がいてディフェンスリバウンドが育つ