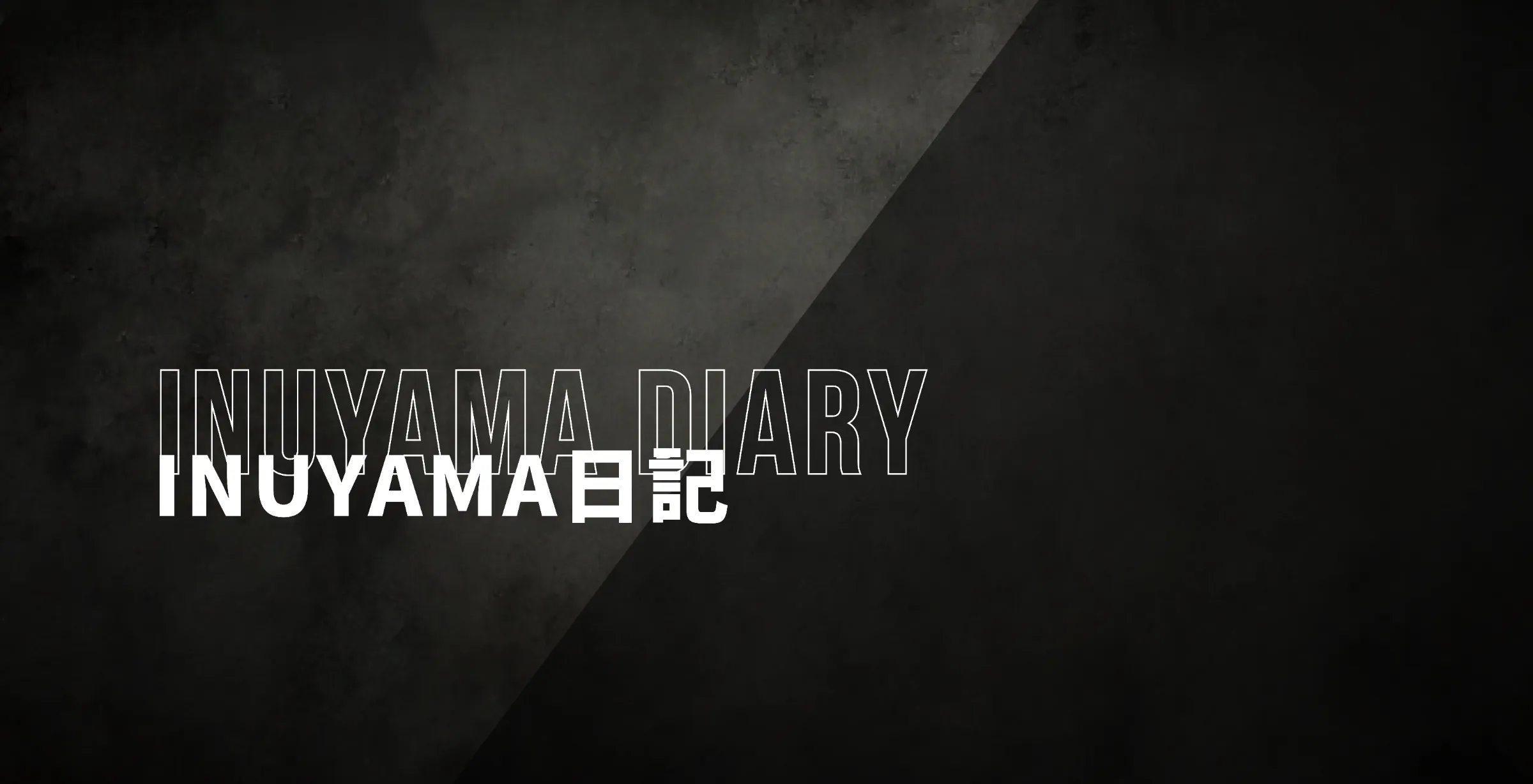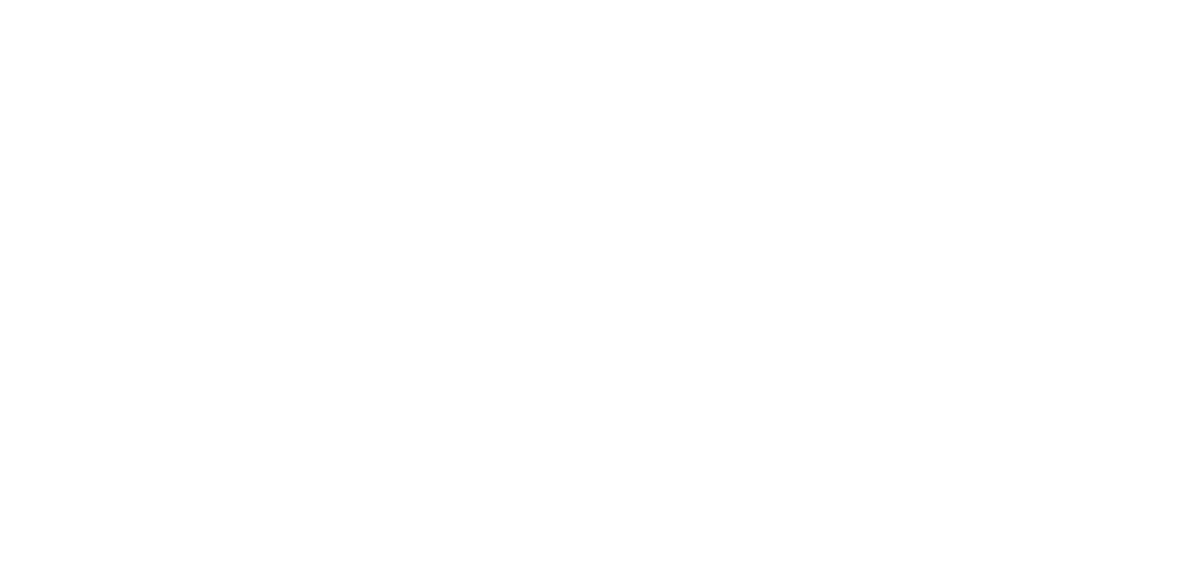#315 仲が良いに潜む罠と力
2025/09/06 16:49

今日は日常の振り返りではなく「コミュニケーション」の観点で自分自身の考え方を共有する記事となります。
これまでの振り返り
INUYAMA BASKETBALL CLUBのヘッドコーチという立場となり5年以上が経ちました。日数にすれば約2,000日程ですがあの頃から今も目の前のことに集中しながら駆け抜けてきたので長いようであっという間の日々です。
ちょうどあの頃はコロナ禍の初期、緊急事態宣言が発令されてしばらくの間体育館で練習することができないところからのスタートでした。世間では3密を避けましょうという周知がされ、Zoom等のオンライン媒体の流行が一気に加速し、INUYAMAでもオンライン練習やInstagramでの練習共有など始めた試みが当時は珍しかったこともあり、様々な方の注目を浴びたことで結果的にたくさんの団員に恵まれ今に至ります。
大切にしたい価値観
三島コーチがこれまで築き上げてきた「バスケットボールを通じて人を育てる」という文化。挨拶、礼儀はもちろんのこと、仲間を大切にする心や感謝の気持ちを忘れないこと。自分一人で成り立っている訳ではないことを常に自覚し、「お陰様」の心を持つことをバスケットを通じて学んでいます。そこに、「100点より100パーセント」というキーワードから全力で打ち込む姿勢の大切さや、「Be a Giver..」というスローガンから与える側の存在になることを個人としてもチームとしても目指すという色を加え、日々の活動に取り組んでいます。
「繋がりを大切に」とよく子供達に話をすることが多いですが、その背景には自分自身がこれまで出会った「人」によって成長をできているからという理由があります。世の中にはたくさんの人が居るので合う合わないはあるものですが、「学べるモノ」は誰にでもあって、吸収できるものは取り入れた方が自分にとってプラスで、否定してしまえばその分の選択肢がなくなるからマイナスだというのが自分の考え方です。
仲間と友達の違い
「仲間」と「友達」の違いについて少し掘り下げてじっくりと考えてみました。今流行りのChatGPTにも意見を求めながら自分なりにいきついたのは以下の整理です。
—
✅「仲間」とは・・【目的】で繋がる関係
・目的や活動を共有している関係
・ゴールや役割を軸につながっている
・個人的な好き嫌いら二の次でも成り立つ
✅「友達」とは・・【感情】で繋がる関係
・個人的な感情の繋がりで結ばれる関係
・一緒にいて楽しい、価値観が合う等
・好き嫌いが強く作用する
—
あくまで僕の考えなので世間の正解ではありません。簡単にまとめると仲間は「目標を一緒に追う存在」であり、友達は「気持ちを分かち合う存在」ということですね。どちらも大切には変わりないですが、環境によって混同してしまうと陥る罠もあったりします。
仲が良いに潜む罠
例えば、職場で働いたり、INUYAMA BASKETBALL CLUBのようなチームに所属していくうえで、「仲間」と「友達」のどちらの関係性の方が組織として好循環になるのか、反対に悪循環になっていくのか。ここの「距離感コントロール」を誤ると総じて「トラブル」のキッカケとなり、「仲が良い」に潜む罠に入り込んでしまうとなかなか抜け出しづらくなります。
距離感が近くなり過ぎることによるリスク(友達関係のリスク)としては、コミュニケーションに遠慮がなくなったり、言葉や態度が雑になったり、相手はこうしてくれると過度な期待をすることで依存が強くなったり、ちょっとした行き違いがキッカケで大きな溝が生まれることもあると思います。
同じ目的を共有しない仲であれば時間薬で(時間が経過すれば)修復することも可能ですが、同じ組織の中に所属をしていた場合、ほとんどは溝が埋まらずの状態が続いてしまいます。
チームに必要な関係性とは
ここからは個人的な考えですが、組織の大小に関わらず、組織に所属するときは近すぎず遠すぎずの「適度な距離感」が大切で、相手を思いやりつつ、自分の感情や立場も理解して、その場をより良い方向へ導いていく「大人な対応」が重要で、距離感マネジメントは組織を運営していくうえでもかなりの重点事項だと感じています。
プライベートでよく遊んだり、飲みに行ったり、一緒に旅行に出掛けたりする友達同士で共通の仕事をしたとき、昔からの友人同士で一緒に企業したことによってその後に起こってしまうトラブルの多くには、総じて「距離感」が影響をしていると思ってます。一方で、INUYAMA BASKETBALL CLUBでのこれまでの経験を踏まえると、本当の意味でチームの一体感が生まれる時は、関係者同士(選手・保護者・スタッフ)が必要以上に仲が良い訳ではなく、干渉しすぎない適度な距離感でいながらも信頼関係や他者に対する敬意で成り立っているため、結果的にはチームとして大きなパワーとなっていきます。
子供達の成長のために
とても長くなってしまいましたが今日の内容は「仲間だと良い」「友達だと悪い」という話ではなく、時と場所によってその使い分けができないと結果的には自分自身や所属する組織を苦しめることに繋がる可能性があり、コミュニケーションには「距離感」が重要であるという学びの共有記事でした。適度な距離感を保てば“仲が良い”はとても大きな力にもなり得ます。
子供たちの成長のために、まずは大人から距離感マネジメントを意識していき、その背中をみて、子供たちもまた健全な人間関係を学んでいく流れをつくれるのが理想ですね🤝